あるときは時空を穿つように鋭い叫びをも感じさせ、またあるときは目もくらむような多彩な音色で天空は潤い、雅、且つ底無しの幽玄までを表現する能の笛―能管。幼い頃聞いた抒情歌の繊細さ、哀愁や優しさや、美しく柔らかな、心に染み入るような人間の自然の感情を自ずと表現できる女竹に穴を七つあけただけの笛―篠笛。この二種類の横笛の魅力の虜になって早20年以上が過ぎた。
何故笛なんかやる気になったのか、といった質問をよく受ける。私が渉外弁護士と言われる分野の業務をしている故か、イメージが旧い伝統芸能の分野とは結びつかないのかもしれない。
平成3年ロンドン出張時に弁護士の自宅に招かれ、夕食を御馳走になった。食後、奥さんがヴァイオリンを弾き、旦那がピアノを弾いた。それがサーの称号を持つ、彼の家のもてなしのかたちだったのだろう。
嫌な予感がしたのは、一緒に招かれたモナコから来た金髪でハンサムな若手の弁護士が、求めに応じて躊躇もせずピアノを伴奏にオペラ、アリアの一節を大声で歌ったときからだった。
彼が歌った後、やはり恐れていたように皆が「ケンジ、お前は何かできるか」ということになった。失礼な、日本男児、俺だって歌ぐらい歌える。「日本の歌でいいか」「勿論!」「伴奏なしでネ」、人前で歌える歌なんて、実は学生時代から年季の入った“人生劇場”だけだ。それを歌い終わったとき、数人の聴衆の反応は複雑というか言い表し難い表情であった。どう反応してよいかわからなかったのだろう。
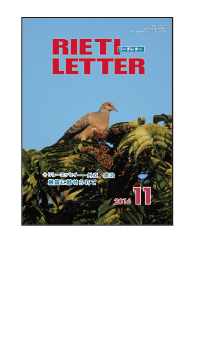
ロンドンから帰国し半年も経たないうちに、今度は当時の駐日アメリカ大使から大使公邸に夫婦で夕食に招かれた。食後また同じようなことが起きた。大使夫人はニューヨークの著名なジュリアード音楽学院を出たプロと言えるほどのピアニストであり、そのときの同伴客は日本商社の役員夫妻。彼は小さい頃からヴァイオリンをやっていたとのことで、ベートーベンの曲を大使夫人と一緒に演奏。さすがの私もそのとき“人生劇場”ではグローバリゼーションにマッチングしないことが分かった。そして何か楽器をやらなくては、やりたいと心から思った。
そんな年の師走、顧問先の会長で、赤坂での伝統芸能を絶やしてはいけないとばかり、よく芸者さんを自分の宴席に呼んでいた方から、或る案件の成功の慰労で接待を受けた。そのときの芸者さんが奏でた凛と響きわたる笛の音に、これこそ捜し求めていた楽器だとすぐさまその席で頼み込んで仲人となってもらい、その芸者さんに連れられて、平成6年1月、プロの福原徹師に弟子入りしたわけである。
当初の一年は音も鳴らず過ぎ、難しい横笛を選択したことに後悔したが、いつかは鳴るだろうと信じ、とにかく毎週末は必ず笛に息を吹き込む作業を続けてきた。そして10年が過ぎた頃、宗家より「福原桜夜」と名乗ること許され、名取の末席に加えられた。それからまた10年が過ぎたが満足のいく笛の音は今も出ない。未熟な笛だが、今後も精進を続けねばと決意を新たにしているところである。