カンボジア和平のプロセスで、日本政府が粘り強く働いたことはあまり知られ
ていない。和平後の社会復興のための国際
協力を持続するために、アンコール遺跡
の保存修復を皆でやろうと働きかけた。私
は、一九九二年からの予備調査を経て、
一九九四年一一月から一○年半、日本国政
府アンコール遺跡救済チーム(JSA)の
団長としてアンコール遺跡の保存修復にか
かわった。文字通り、“戦いすんで日が暮
れて”の心持ちであった。アンコール遺跡と
いえば、調査研究と保存修復ともフランス
の独壇場であったが、JSAもこの分野の
日本のパイロットプロジェクトとしての意
気込みも高く、人材養成、総合的学術情報
の公開、オリジナルな工法を尊重した精緻
な修復工事において、自他ともに認める成
果をあげた。アンコールは危機遺産から解
除され、観光客も急増している。とはいえ、
アンコールは膨大な遺跡であり、アンコー
ル・ワットとバイヨン寺院でさえ、まだま
だ永続的な保存は至難な技である。まして
は、カンボジアの密林の奥へ行くと、大き
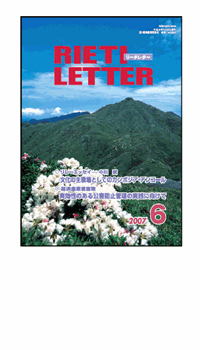
な構想力によって構築された、人類の至宝
ともいうべき大遺跡が、略奪と崩壊のまま
無惨に放置されている。これらの遺跡を訪
ね歩くうちに、土地に根付くことの豊かさ
と人間の精神の高みで結び合うユニバーサ
ルな感覚を、感じるようになった。この十
数年の間、アンコール・ワットとバイヨン
の具体的な半解体再構築の修復工事で遺構
の内部構造に触れることによって、同様の
感慨を持ったが、このような感覚がカンボ
ジア全土にネットワークのように広がって
いたのである。そしてこのアトモスフェア
はラオスのワット・プー、タイのスコータ
イ(いずれもアンコール期の遺跡)、ベトナ
ムのミーソン(チャンパ)やメコンデルタ
のオ・ケオ(フーナン)でも感じたことだっ
た。これらの地域が一二〜一三世紀のアン
コール朝の最大の版図に重なるからではな
く、実は、インド・シナあるいは東南アジ
ア的なものの基層にアンコール的感覚が流
れているからではないか。アンコール朝の
文化・文明の骨格は間違いなくインド伝来
のものである。しかし、アンコールのそれ
が、自ずと周辺環境に溶け込み易いように、
細部を融通無碍に省略したり、大きな空洞
を内部に包含していたりするために、イン
ド的なものと形態や形式の類似性は強いが、
雰囲気が決定的に異なる。これは、インド
からの文化をカンボジアの風土の中で変形
したのではなく、この地に本来的なるもの
が甦った、つまり、インドと中国という古
代文明の中心から周縁的な地ゆえに、古代
以前のものが保存されたのではないか。二○世紀が革命と戦争の世紀であったとすれ
ば、その一方の旗頭であった共産主義運動
の鬼っ子とでもいうべきポル・ポトがこの
地を席巻したことは、共産主義が近代の彼
岸と原始への復帰を併せ持っていたことと
無縁ではないだろう。そして、二一世紀の
課題の中心が、極限まで来てしまった開発
と対立の人類的、地球的規模の調停にある
のだとすれば、アンコールの佇まいにこそ
重要な示唆がある。そのたたかいを再度先
導すべき役割が日本にはあるだろう。


![]()